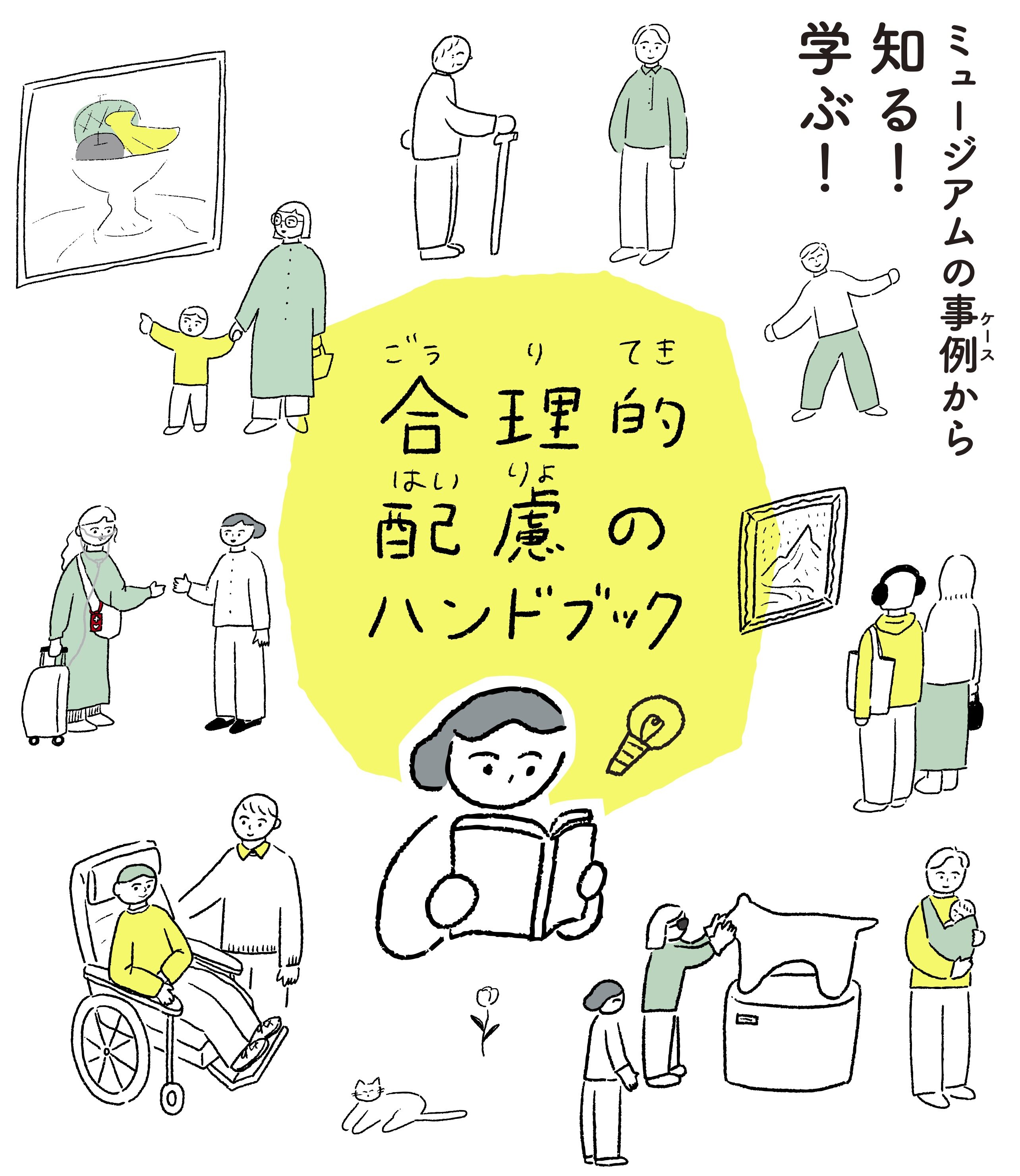〔概要説明〕
独立行政法人国立美術館 国立アートリサーチセンターが、2024年3月に刊行した「ミュージアムの事例(読み方は、ケース)から知る!学ぶ!合理的配慮のハンドブック」を視覚障害に対応するために編集した、音声読み上げ用テキストです。
ハンドブック本体のサイズと仕様は、B5変型の40ページです。
音声読み上げ用のページのリンクは3ページに分かれています。
このページは、ハンドブックの概要説明から7ページまでの音声読み上げ用テキストです。
8ページから25ページまでの音声読み上げ用テキストは、以下のリンクをクリックしてください。
https://ncar.artmuseums.go.jp/reports/d_and_i/post2025-2495.html
26ページから裏表紙までの音声読み上げ用テキストは、以下のリンクをクリックしてください。
https://ncar.artmuseums.go.jp/reports/d_and_i/post2025-2538.html
ハンドブックのページ数、構成内容に見出しを付けています。例えば【1ページ】、【タイトル】、【奥付】などと記しています。
本文テキストは基本的に「ですます調」で書かれています。なお、テキスト情報でわかりやすくするために、本文を編集している箇所があります。例えば、本文にある日本語の後ろに英語表記やカタカナ表記がある場合は、以下2つの例の通りに記しています。
例1:公平性(英語で、Equity)
例2:多数派(カタカナ表記で、マジョリティ)
視覚情報に関する補足説明は「である調」で統一しています。本文に加えた説明の冒頭には「製作者注:」と記しています。図やイラストなどの非テキスト情報は、補足説明の前に〔図やイラストの説明〕と、後に〔説明、終わり〕と記しています。本文内で記号による箇条書きとなっている箇所は、項目の区切りを示すために数字に置き換えています。
〔概要説明、終わり〕
〔ハンドブックの内容ここから〕
【表紙】
〔レイアウトの説明〕
中央に手書き文字でタイトルが書かれており、タイトルの下には本を読む人物のイラストが描かれている。
タイトルや本を読む人のまわりには、小さな子どもが絵を指さして大人と一緒に見ている様子や、イヤーマフをつけた人が誰かと一緒に並んで絵を見ている様子、サングラスをかけた人が彫刻作品を触っている様子、酸素ボンベをもった人が誰かと話している様子などが描かれている。それ以外に、杖をついた高齢の人、青年、小躍りしている人、赤ちゃんを抱きかかえた男性、車椅子に乗った人と介助者などがタイトルをぐるりと囲むように描かれており、多様な人が美術館を楽しんでいる様子を表現している。
〔説明、終わり〕
【扉1ページ】
「合理的配慮」という言葉を聞いたことはあるでしょうか?
このハンドブックでは、ミュージアムで実際に起こったケースを通して、「合理的配慮」という概念について学び、考えていきます。〔脚注〕このハンドブックでの「ミュージアム」は、美術館を含め博物館法に基づく博物館全般を対象としています。〔これはページ末にある脚注、終わり〕
ミュージアムには、毎日たくさんの人が訪れます。
一人で来る人、こどもを連れた人、日本で生まれた人、海外にルーツがある人、障害がある人、障害のある人に寄り添う人……
ミュージアムを訪れる人に制限はありません。
ミュージアムを楽しむことは、だれもがもつ権利です。
しかし、時としてその人その人の特別な状況やニーズに対応がないために、その権利を平等に受けられない場合があります。
そこで大切になるのが「合理的配慮」です。
ミュージアムではたらく人を含め、そこに関係する人々が「合理的配慮」を理解し、提供すること。
そのことが法律で義務化されているのを知らない人も多いかもしれません。
言葉が難しいためにちょっとわかりづらい「合理的配慮」。
この大切な概念について、ハンドブックを通して、一緒に考えていきましょう。
【扉2ページ】
「合理的配慮」を提供することは法律によると……
第7条の2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、
第8条の2 事業者は、その事業を行うに当たり、
障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
障害者差別解消法(平成25年公布 令和3年一部改正)より
〔イラストの説明〕頬杖をついた人物の頭の上に疑問符を浮かべたイラストが描かれている。〔説明、終わり〕
【3ページ】目次
「合理的配慮」を考える前に
なぜ、今「合理的配慮」なのか?/どこに障害があるの? 人のせい?ミュージアム、社会のせい?/どうやって解決するの? 個別のニーズへの対応/ハンドブックの目的
4ページから7ページ
「合理的配慮」実現までの3つのプロセス
8ページ
ミュージアムのケースから考える合理的配慮
ケース1 聞こえないIさんが、講演会に参加したい
ケース2 見えないHさんが、作品を鑑賞したい
ケース3 フルリクライニング式の車椅子に乗ったCさんが、移動するためにエレベーターを利用したい
ケース4 重度の身体障害のあるJさんが、大人用のオムツ替えができるトイレを利用したい
ケース5 発達障害のあるTさんが、安心して展示を見に行きたい
ケース6 発話しづらいSさんが、電話以外の方法で問い合わせをしたい
ケース7 内部障害のあるOさんが、酸素ボンベをミュージアムで交換したい
ケース8 赤ちゃんを連れたYさんが、授乳をしたい
9ページから25ページ
「合理的配慮」のポイント
「対話」の重要性/調整、変更/工夫できる範囲で/「特別扱い」ではなく、社会的障壁をなくすこと
26ページから27ページ
「合理的配慮」が実現されなかった事例
施設のハード、ソフト面がないことを理由に断るケース/ルールの変更を検討せずに断るケース/個別のニーズへの対応がされないケース
28ページから29ページ
だれもがミュージアムを楽しむ「権利」を守るために
ミュージアムと人権の保障/公平性(英語で、 Equity)と平等性(英語で、Equality)の違い
30ページから33ページ
参考文献、ウェブサイト/「DEAIリサーチラボ(読み方は、であいリサーチラボ)」とは
34ページ
【4ページ】「合理的配慮」を考える前に
なぜ、今「合理的配慮」なのか?
「合理的配慮」とは、障害者の権利をはばむ社会的障壁を除去するために、個別の状況に応じて必要かつ適当な、変更や調整をさします。
この考え方は、2006年に国際連合の総会で採択された「障害者権利条約」で明文化されました。日本ではこの条約に批准するためには国内法を整備する必要があり、2013年に「障害者差別解消法」が成立しました。この法律では、国をはじめとする公的機関、自治体は「合理的配慮」の提供を行うことが義務化されています。加えて、法改正により2024年4月からは民間事業者も含め完全に義務化されることになりました。
障害者から個別の状況を聞き対応していく「合理的配慮」は、21世紀において国際的にも標準の考え方であり、「共生社会」を実現するうえでも重要な概念です。
どこに障害があるの? 人のせい? ミュージアム、社会のせい?
「障害がある人」「障害者」と聞くと、どのようなイメージを思い浮かべますか?
一般的に「目が見えない」「耳が聞こえない」「立って歩けない」などの身体や精神面の機能に違いがあることを「障害」だと捉えがちですが、実はよく考えると、社会や環境のあり方、仕組みが「障害」をつくり出しているともいえるのです。
例えば、耳の聞こえない人がミュージアムで行われる講演会を楽しみたいとき、何が障害になるのでしょう?5ページの「障害の個人モデル」とは、障害を医療、福祉の領域の問題だと捉え、耳の聞こえない人が補聴器をつけたり手術を受けたりして「聞こえる」状態に治すなど、個人の努力や訓練などで対応するという考え方です。それに対して「障害の社会モデル」とは、社会や組織の仕組み、文化や慣習などが多数派(カタカナ表記で、マジョリティ)の都合でつくられているために、障害者など少数派(カタカナ表記で、マイノリティ)との間に「社会的障壁(カタカナ表記で、バリア)」となる障害ができているという考え方です。つまり、社会が「障害」をつくり出していると考え、それを解消するのは社会の責務だと捉えます。先ほどの例で考えると、耳の聞こえない 【5ページ】 人が講演会に参加できない「障害」が生まれた場合には、ミュージアムが手話通訳の手配や筆談対応を行うなどして、この「障害」を解消する必要があるということです。
このハンドブックでは、「障害の社会モデル」という視点に立って考えていきます。ここで取り上げる「障害がある人」というのは、障害者手帳を持つ人だけではなく、ミュージアムへ行くときに何らかの「障害」があると感じる人を指します。さらに障害者差別解消法では、障害者手帳を持つ人に限らず心身のはたらきに何らかの障害がある人が合理的配慮の対象とされていますが、ここでは、対象を広く捉え、さまざまな社会的障壁がある事例も含めています。心理的、経済的、文化的な場面において社会的障壁を感じる、あらゆる人の「ミュージアムでの困りごと」を可視化し、その「障害」をなくすことに一歩でもつなげることがねらいです。
〔図の説明〕
⾞椅⼦に乗った⼈が、階段の前に立っている状態の図が2つある。
上の図は、⾞椅⼦に乗っている本⼈に⾚⾊が付いていて、階段をのぼれない原因が本⼈そのものにある、とする「障害の個⼈モデル(別名は、医学モデル)」を表した図である。障害や困難、不利益が生まれるのは、個人の身体面、精神面の機能が原因であるという考え方を示している。
それに対して、下の図では、階段の⽅に⾚⾊が付いていて、階段をのぼれない原因が、多数派を前提に作られた社会の状況や仕組みに原因がある、とする「社会モデル」を表した図である。
〔図の説明、終わり〕
【6ページ】どうやって解決するの?――個別のニーズへの対応
障害がある人への対応として、日本では1990年代以降、ハートビル法やバリアフリー新法の制定などにより、ミュージアムにおいて主に環境、施設面での対応が進められてきました。
具体例として、
「車椅子に対応したスロープを設置する」
「視覚障害に対応した点字ブロックを設置する」
「聴覚障害に対応した筆談ボードやヒアリングループを設置する」など、さまざまな障害がある人に対応できるように設備を整え、「バリアフリー」の考え方もずいぶん浸透してきました。
加えて、ワークショップやイベントなどで対応する実践事例も増えてきました。例えば、「手話通訳付きのギャラリートーク」や、視覚障害のある人が触りながら楽しむための「触るツール」、認知症の人も参加できる認知症フレンドリーな企画など、設備面だけでなく多様な層の人がミュージアムを利用できることを目指す取り組みも増えてきました。
しかし、これらは「不特定多数」の人の来館を想定して対応しているものです。いわゆる施設のバリアフリー化やプログラムの企画などは、「環境の整備」と呼ばれ、全体に対応した取り組みであって、個別に対応する「合理的配慮」とは異なります。
もちろん、「環境の整備」により来館のハードルが下がったり、多様な人がミュージアムにアクセスする機会が増えたりすることは間違いありません。ただし、全体への対応だけで一つひとつの「社会的障壁」がなくなるわけではないのです。全体への対応と合わせて、個別のニーズに応えるために「合理的配慮」が求められています。
【7ページ】
〔図の説明〕
障害がある人への対応として、「環境の整備」と「合理的配慮」の違いが左右の図で示されている。中央には「掛ける」ことを意味するバツ印のマークがある。
左図では、バリアフリー法などによる、全体の対応、環境の整備の例を、以下6点挙げている。
1 スロープの設置
2 点字ブロックの設置
3 筆談ボードの設置
4 手話通訳付きのギャラリートーク
5 触察(読み方は、しょくさつ)、触図ツール(読み方は、しょくず)の開発
6 認知症フレンドリーの取り組み
右図では、障害者差別解消法による、合理的配慮の例を、以下2点挙げている。
1 聞こえないAさんから通常の講演会に参加したいという要望があったので手話通訳を手配した。
2 見えないBさんから作品を触りながら鑑賞したいという要望があったので触るツールを用意した。
〔図の説明、終わり〕
ハンドブックの目的
このハンドブックでは、ミュージアムを利用するときに「障害(すなわち、社会的障壁)」を感じるあらゆる人に対して、ミュージアムが対応できるようになること、つまり対話のある「合理的配慮」が実現されるようになることを目指しています。
国立アートリサーチセンターでは2023年8月に35ページ参照の「DEAI(読み方は、であい)リサーチラボ」を立ち上げ、ミュージアムで実際に起こった「合理的配慮」の事例を集めました。集めた事例をもとに、ラボメンバーがミュージアムにおける「合理的配慮」について、約半年間かけて検証と議論を重ねてきた内容がまとめられています。
ハンドブックを通じて、ミュージアムに関わる人が「合理的配慮」の理解を深め、さらに行動変容を起こすことを目的にしています。だれもがミュージアムを利用できる公平な場にしていくために、そしてその先にある共生社会を実現するために、私たちは「合理的配慮」について理解する必要があるのです。
次のページに続きます。ハンドブックの8ページから25ページまでの音声読み上げ用テキストは、以下のリンクをクリックしてください。
https://ncar.artmuseums.go.jp/reports/d_and_i/post2025-2495.html