討議


- 日時:
- 8月2日(日)16:25~17:10
- 司会:
- 東良雅人(文部科学省 教科調査官)
- 討議者:
- 逢坂恵理子(横浜美術館 館長)
奥村高明(聖徳大学 教授)
長田謙一(名古屋芸術大学 教授)
三澤一実(武蔵野美術大学 教授)
鑑賞教育のこれまでとこれから

私と鑑賞教育
- 東良:
- 本日は「美術館を活用した鑑賞教育充実のための指導者研修」の10周年記念シンポジウムということで、冒頭、一條さんのほうから10年間の振り返り、逢坂館長のほうから鑑賞教育のこれからの在り方も含めたいへん示唆に富んだお話、そしてこの10年間でこの研修を受講してきたみなさんの発表から、これまでのこの研修の受講経験を生かしてどのように普及させていくかというようなお話をいただき、臨場感あふれるかたちで前半が進められたのではないかと思います。
- 後半は限られた時間ではありますが、「鑑賞教育のこれまでとこれから」というテーマのもと、4名のシンポジストの方に、それぞれのお立場からお話を伺っていきたいと思います。本日の一連の流れをまとめていくようなお話になればと思うとともに、10年が経過したこの指導者研修の次のステップとして、どういったことを考えていったらよいか、その足がかりとなるような時間になればと思っています。これは、いま私の手元にある開講当時の冊子ですが、今日のシンポジウムはこの10年の長い活動のなかでひとつの区切りになろうかと思います。
- まずは自己紹介等もかねて、「私と鑑賞教育」といったことについてお話しいただければと思います。それでは最初に本日の講演をいただきました逢坂館長からお願いします。

- 逢坂:
- さきほど私と鑑賞教育のかかわりは少しお話ししたので、かいつまんでお話しします。私が学芸員の仕事を始めましたのは、現代美術の世界でした。現代美術の世界というのは私たちと同世代のアーティストが生きていますが、既成の枠組みを超える表現や私たちの先入観を超えるような表現に出会った時、まずは自分がどういうふうに鑑賞し伝えていくかという課題がありました。わからない作品にどうやって向き合っていこうか、伝えていこうかという時に、ひとつの事例となったのが、ニューヨーク近代美術館の「ビジュアル・シンキング・カリキュラム」です。作品から、まず描かれているものをじっくり読み取って、自分たちの言葉に置き換えて、グループでいろいろ意見を交わして、ひとつの鑑賞を構築していくという方法でした。慣れてくれば、自由に、それこそ作家の意図も超えて鑑賞することができるのが美術鑑賞のおもしろみですし、とくに子どもたちは大人の気づかなかったようなことを自由に発想してくれたりもするので、アーティスト、それから子どもたちから鑑賞のおもしろみを間接的にまた直接的に得ることができたかなと思います。それを整理することができたのが、ニューヨーク近代美術館の教育担当の方々との出会いでした。その後、それを日本でどういうふうに発展させるか、現場の教育担当の人たちと模索してきた、というのが今日となっています。
- 東良:
- ありがとうございました。それでは次に、奥村先生、いかがでしょうか。
- 奥村:
- 私と鑑賞教育ということについては、まず1980年代に小中学校教員として図工や美術の授業で鑑賞をしています。次に2000年代に県立美術館の学芸員でギャラリートークやアートゲーム、鑑賞行動の研究などをしました。2005年より文部科学省で学習指導要領や鑑賞教育の指導に携わりました。その後、2011年から大学で鑑賞教育の研究や教材開発をしています。基本的に現場人なので、こういう教育の現場に来るだけでわくわくどきどきしています。よろしくお願いします。
- 東良:
- ありがとうございました。それでは長田先生、お願いいたします。
- 長田:
- 私の専門は、芸術学と美術教育と、そのあいだをつなぐ美術館教育と、アートマネジメントという、各領域にまたがったようなところがあります。とりわけいま勤めている大学の前の前、千葉大学に勤務していたころ、学生たちとともに、美術館と学校と大学をつなぐような一連のプログラムを授業に組み入れて展開するようになってから、鑑賞教育のアクティビティとはいちばん密接な関わりをもってきたように思います。そのきっかけになったのが、1985年にミュンヘンとベルリンに1年間留学して、ドイツにおける美術館教育の先進性というものに触れたことです。
- 日本に戻ってきてからは、まず、美術館教育のたかまりを拓きつつあった各方面の方々と連絡をとって、《日本独逸美術館教育──シンポジウムと行動》の企画に関わりました。さらに、東京都図画工作研究会の先生方と連絡をとったり、当時、一條さんの前の勤務先であったセゾン美術館(1999年閉館)のプログラムに関わらせていただいたり、すでに日本で始まりつつあった美術館教育のいろいろな動きとリンクしながら、なにか面白い動きを日本で醸成することができないだろうか、それに自分なりに力を注ぐことはできないだろうかと、やってきたわけです。逢坂さんのもとで、水戸で開かれた日本・ドイツ・イギリスの美術館および美術館を越えたエリアでの、草の根的な芸術振興の動きのシンポジウムにも参加させていただいたりしていることをバックにして、この研修の企画にも最初から関わらせていただきました。現在は名古屋芸術大学に勤めております。
- 東良:
- ありがとうございました。それでは三澤先生お願いいたします。
- 三澤:
- 武蔵野美術大学の三澤と申します。いまから25年ほど前の話になりますが、私は大学を出たあと中学校の教員からスタートしたのですが、最初に赴任した中学校が廊下を自転車が走っているような学校でした。幸いなことに美術の教員が3名いたので、その状況をどうにかしようと、鑑賞教育で心を育てようとなりました。当時ほとんど実践事例がなく、手探りのなかで鑑賞教育を始めたのです。授業で「彫刻からのメッセージ」という、現代彫刻の作品を鑑賞した時、ふだんまったく言うことをきかない生徒が非常にユニークな発言をして、それがぜんぜん間違っていないんですよね。「ああ、この子がこういう発言をするのか」と、子どもを捉える目ががらっと変わって、鑑賞っておもしろいな、と。それからいままでずっと来ているわけです。中学校を10年経験しまして、埼玉県立近代美術館を1年、それから文教大学、武蔵野美術大学にきて8年目になります。
- 現在は、さきほどもご紹介がありましたけれども、「旅するムサビ」というプロジェクトで、全国の小中学校に学生が作品を持っていって、図工や美術の時間で対話による鑑賞教育をしながら子どもたちと触れあっております。最近では「黒板ジャック」という、子どもたちを驚かせる活動もしております。先々週も奄美に行ってきまして、全校児童9名の小学校で黒板ジャックを展開してきました。
- 美術というのは、「みる」とか「つくる」とか、その場の体験でしか伝わらないなとつくづく感じておりまして、この研修でも、「体験する」「経験する」ということが、鑑賞教育の広がりをつくっていくんだなと感じました。よろしくお願いします。
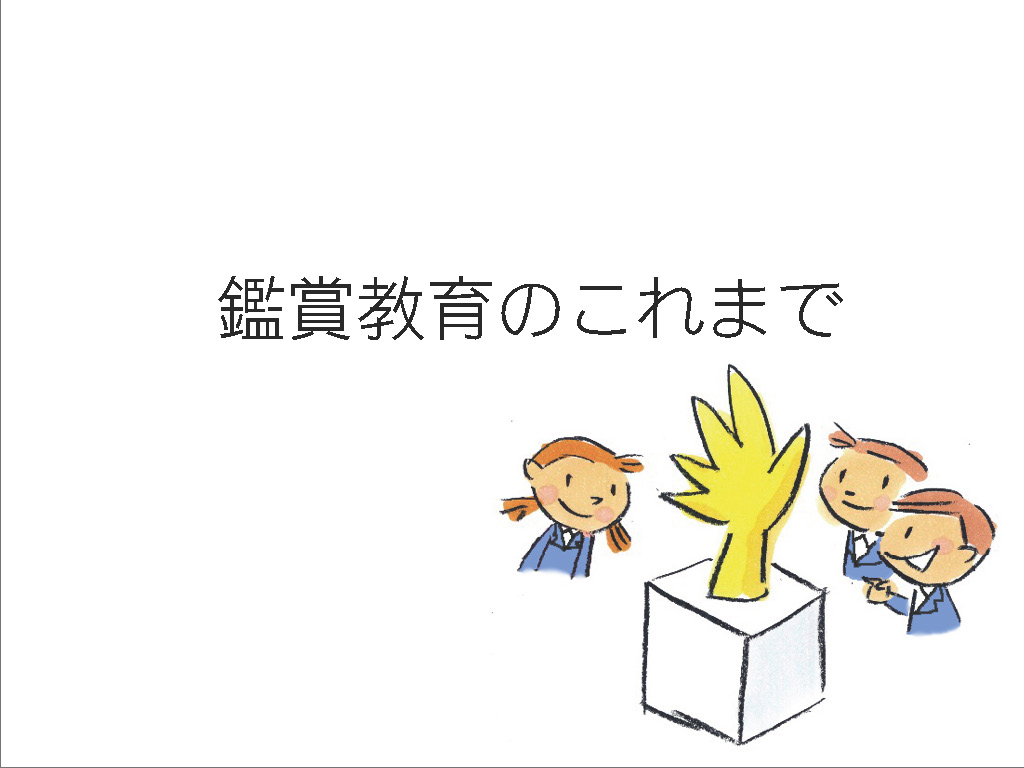
鑑賞教育のこれまで
- 東良:
- それでは、このシンポジウムの討議のタイトルにもあります「鑑賞教育のこれまで(とこれから)」ということで、先生方からお話を聞かせていただこうと思います。今日最初に一條さんのほうからありましたように、この指導者研修がスタートした2006年は、学習指導要領のなかで鑑賞教育が重視されていく時期とリンクしているところもたくさんあるわけです。例えば、平成10(1998)年の答申(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程の基準の改善について)の改善の基本方針では、これまではどちらかというと表現活動に関わる内容が中心で答申されていたものが、「豊かな表現活動や鑑賞活動をしていくための基礎となる資質・能力を一層育てられるようにする」「各学校段階の特質に応じて、我が国やアジアなど諸外国の美術文化について関心や理解を一層深められるように鑑賞の充実を図る」ということ、それから「その際、地域の美術館等の活用を図るように配慮する」ことなどが示されました。また、この時の中学校の美術の具体的事項には、(ウ)の事項「我が国及び諸外国の美術文化や表現の特質などについての関心や理解、作品の見方を深める鑑賞の指導が一層充実して行われるようにする」ことや「その際、我が国の美術についても重視する」こと、「また、『鑑賞』に充てる授業時数を十分確保するようにする」ことなどが示され、鑑賞教育の充実が言われはじめた時期と時を同じくしながらこの研修がスタートしました。
- 平成20(2008)年の答申(幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領の改善について)の改善の基本方針では、鑑賞の学習を通して、どういった力をつけていくのかということに重きが置かれ、そのなかで、自分の価値意識をもって批評する、思いを語ることや、感じ取る力、思考する力を一層重視することなどが示されました。これは、鑑賞の学習の充実とともに奥村先生が教科調査官だった時に改訂した、現行の小学校図画工作のなかの内容の取り扱いにおいて、「地域の美術館などを利用したり連携を図ったりすること」が示されているなかで、学校現場、美術館、そして様々な人たちの努力の積み重ねを通して、今があるのだと思います。
- 今度は「これまでの鑑賞教育」を、ここで今一度振り返り、どういった苦労──この研修をつくるにあたっての苦労や美術館としての様々な取り組みの苦労もあったでしょうし、そういったものを含めてこれまでの鑑賞教育について──、少しこの場を借りてお話聞かせていただければと思います。
- 奥村先生、いかがでしょうか。
- 奥村:
- 鑑賞教育のこれまでについては、この「美術館を活用した鑑賞教育充実のための指導者研修」のプロセスをお話しすれば、この10年の流れをお伝えできると思います。10年前当時に国立美術館の存立基盤が危ない時期があり、残りはしたけれども国全体にどのように貢献するかというオーダーがあったそうです。それで、立ち上がったのが学校との連携、普及活動の充実を図るための委員会で、その座長に私が指名されました。
- 大きなオーダーはふたつありました。鑑賞教育の本や教材の開発がひとつ。そこでつくった教材が「アートカード」です。もうひとつが、この指導者研修なんです。その内容は、長田先生もお詳しいんですが、当時国立美術館よりも地域のそれぞれの美術館や地域の先生たちの方がかなり独創的で創造的な取り組みを何十年もやっていました。でも、地域や個人のノウハウは単発で終わっていました。そこで、地域のノウハウを集めたら何かムーブメントを起こせるのではないか、国立美術館は地域の実践同士をつなげる結節点になれるのではないか、というのが指導者研修のスタートでした。
- みんなが集まって、それが散らばったら何かが起きて、それが広がっていくだろうというのが、私たちの考えだったんですけれども、最初に集まった130人ほどの参加者のなかには、「鑑賞? 何?」という参加者もいれば、ものすごくおもしろい実践をしている参加者もいて、かなり幅がありました。ところが、毎年毎年繰り返すたびに内容や参加者の発言が変わっていくんです。みるみる変化していきました。もちろんさきほど東良調査官からお話があったように、平成10(1998)年の学習指導要領の改訂もありましたし、それぞれの美術館も普及活動を活性化しなくてはいけないという状況もあったと思います。様々なことが連動して鑑賞教育が豊かになっていったということが、おそらくこれまででしょう。そこで平成20(2008)年の学習指導要領の改訂では、それまで単に美術館の「利用」だったものを、その実態を踏まえて美術館との「連携」にすることができたわけです。
- 仕掛けたほうとしては、アートカードは当時3つか4つしかなかったのに、いまやどこでもあるでしょう。アートカードがない美術館や地域を探すほうがむずかしい。そしてギャラリートークも改善されました。会話型、対話型、あるいはディスカッション型、いろんな方法があります。それから委員会では書籍までは出版できませんでしたが、長田先生と私でテートギャラリーの『美術館活用術 鑑賞教育の手引き』(美術出版社、2012)という翻訳をしました。今は、それ以上に鑑賞教育についていろいろな会社からいろいろな本が発売されています。本も出版され、アートカードも充実し、対話的なかたちにギャラリートークも改善された、でも、それぞれの方法に長所と短所があります。それがこれからの課題で、今後改善していく流れになるだろうと思います。
- 東良:
- ありがとうございます。では長田先生お願いします。
- 長田:
- いま、奥村先生がお話しされた前のところから少し振り返ってみたいと思います。1980年代初めまでの日本の美術館事情のなかで、ミュージアム・エデュケーションは立ち後れていて、それに関わる方々はまだまだ肩身が狭いという状況があったと思います。しかし80年代に新しくできた美術館の学芸の方々から意欲的な人が出てきたり、あるいは美術館勤務ではないけれども、美術館教育を海外に学びながら研究しようという動きも起きたりして、ようやく日本で美術館のエデュケーショナルな活動のうねりが起こりはじめた。90年代末までには、そのような先駆的な例が、奥村先生が言われたように、日本各地に生まれていて、しかしまだ十分つながりあってはいなかった、ということだったと思います。他方、学校でも、「鑑賞」は取り組みにくい、美術史の勉強をして教えなくてはいけない、というような印象がどうしても強くて、制作中心の時間のなかで、鑑賞の位置づけは、非常にむずかしい状況があった。
- この双方が大きく変わっていく決定的な力になったのが、この10年間の研修だったのではないでしょうか。この10年間そのものに光をあてて考えてみると、美術館と学校が連携して鑑賞教育を行っていくアプローチの仕方に、性格や起点やうねりのちがう波がいくつか重なって10年間を構成してきたように私には見えます。ひとつは、この10年間の研修が始まる前に各地で展開してきたミュージアム・エデュケーションのたかまりです。ここで、なおマイナーではあるけれども前景化していったのは、ワークショップ的活動を核としたミュージアム・エデュケーションでした。東京都図画工作研究会のみなさんといっしょに私も翻訳に関わった、ドイツのシュプレンゲル美術館のワークショップをドキュメントした本の翻訳『芸術あそび : ワークショップつくるみる/美術ハンドブック』(日本文教出版、1996)などにも典型的に示されているように、子どもたちのワークショップ的なアクティヴィティ、これがエデュケーション・プログラムの中心になっていて、新しい美術館がワークショップ的な活動を前景に押し出しながら、美術館におけるエデュケーション・プログラムそのものを前景化していくことになりました。
- ところが90年代末以降、今日逢坂さんがニューヨーク近代美術館の活動の蓄積を紹介されながら詳しくお話しくださったように、日本に「対話型の鑑賞教育」──作品それ自体を観る側が能動的に読み取って、自分自身の目で深く理解をしていく対話的なエデュケーショナルな活動が、鑑賞教育の次の波を構成していきます。この波は、美術館教育の波であるとともに、学校美術教育における鑑賞教育の重視・新展開というもうひとつの波でもありました。この研修が成立した時は、日本におけるミュージアム・エデュケーションのふたつの波、さらには学校における鑑賞の波がちょうど重なるような時であり、またそのような重なりを強く意識して、学校と美術館の連携を意図して研修が企画されたのでもあります。研修では、「対話型鑑賞」はいわば共有されながら、それに尽きない色々な試みや、あるいはそれに伴う部分的反省などが蓄積され、日本の学校──美術館の感傷的プログラムを成熟させ、対話型の鑑賞をベースにしながら、それがさらに、つくったりといったアクティヴィティと深くリンクする新しい段階をも開きつつあるように思えます。
- 東良:
- ありがとうございます。いま長田先生のお話のなかにありましたが、逢坂館長、今日のお話にあった「みる、つくる、まなぶ」についてのこれまでの流れ、そのあたりも含めて鑑賞教育のこれまでについて、美術館のお立場でお話しいただけますか。
- 逢坂:
- さきほどもお話ししましたように、私自身の学芸員としてのキャリアをスタートしたのは水戸芸術館というところでして、水戸市は25万人の都市です。そのあと六本木の森美術館に移りまして、そこは東京ですから1300万人の都市、そして横浜市が370万人の都市なので、ひとくちに美術館の事業といっても、ぜんぜんちがうんですね。
- 私が対話式の鑑賞に出会ったのは水戸芸術館時代で、90年代最初の頃でした。まずは展覧会会場に子どもたちに実際に来てもらっていっしょに対話したいと思って、近隣の学校に相談をしに行った時、先生に、「水戸芸術館に行く手立てがない」と言われたんです。東京などの大都会に住んでいるとまったく感じないことなんですけれども、まず、美術館までの電車がないんですね。そして車社会である。そんななかで、私たちがまず最初にやらなくてはいけなかったのは、バスを仕立てることだったんです。地方都市の美術館では、そういうことをしないとなかなかお客様が来てくださらないという状況が今でもあるかもしれませんが、「バスを仕立ててお迎えにいくので、水戸芸術館に来てくれませんか?」ということからスタートしたことを思い出しながら先生方のご報告を聞いていますと、美術館に来るということが違和感なく先生方のなかに浸透した、もしくは学校教育のなかに位置づけられたんだなという思いがあります。
- そして、そこからどういうふうに多くの学生たちに美術の現場を知ってもらうかということは、今、長田先生がおっしゃったように、現在少しずつ変わってきていまして、鑑賞教育の在り方について、各美術館で、そして各先生方のなかで、いろいろ模索し、実践し、あるべき姿に育ってきている、その過渡期なんだろうなと思います。そういう意味では横浜美術館は幸い造形活動のできる施設が整っていまして、そのためのエデュケーターとして、実際に作品をつくる指導をしてきた人たちが、鑑賞教育とは一歩ちがうところで美術教育に心を砕いてきました。そして、私が入ってから、鑑賞教育を担う教育プロジェクトチームを立ち上げましたので、「市民のアトリエ」で造形を指導するインストラクターが正職員3名、「子どものアトリエ」の正職員が2名と期間限定のアシスタントが1名、そして鑑賞ということだけに特化して行う学芸員の資格のあるエデュケーターが3名いまして、教育プロジェクトチームだけでも9名いるわけです。これは日本のほかの美術館と比較しても、非常に恵まれている状況なのではないかと思います。これだけ美術館教育や鑑賞教育が学校と連携しつつみなさんのなかに浸透してきた状況で、なおかつ学校の指導要領にもきちんと謳われる時代になったからには、それを推進していく専門家たちがより求められているのではないかなと思います。
- 東良:
- ありがとうございます。学校教育のなかに鑑賞教育が位置付けられる、そういった10年間であったということ、それにはハードの面、ソフトの面、両面がむずかしいことを乗り越えてきたということがあるんだろうと思います。そんななかで、三澤先生は徹底した現場主義でやってこられた実践者というふうに私はイメージしているんですけれども、いまのお3人のお話を受けて、いかがですか。
- 三澤:
- まったくそのとおりだと思います。ふたつ大きなポイントがあると思います。ひとつは学校週5日制です。週5日制になる前年に私は埼玉県立近代美術館に勤めていましたが、県のほうから、土曜日に子どもたちを美術館で受け入れられるようにしなさいというお達しが来たわけです。ちょうどその頃、美術館自体も危機的な状況で、入館者数を増やすために子どもたちを美術館に呼ぶ必要があった。また、学校教育も平成14(2002)年から学習指導要領が変わったことで、鑑賞の充実が求められるようになってきた。その両者が困っている段階で、連携が見いだされたのかなという気がします。
- 当初はみな暗中模索で何をやったらいいかわからなかったのですが、それを10年かけて整理していったのだと思います。まだ整理は完全にはできていないですが、印象深かったのは、一條さんの報告にあった長野県の先生の言葉、鑑賞教育という言葉が通じるようになったという言葉が、この10年間を象徴しているな、と思います。対話型鑑賞とか教育普及プログラム、エデュケーション、エデュケーター、そういった言葉が浸透するのに10年かかった、そんな気がします。

鑑賞教育のこれから
- 東良:
- ありがとうございました。そういった意味でも、鑑賞教育という言葉が通じるようになった。量的な面では大きな変化があった10年間だったと思います。最後に、鑑賞教育のこれからということで、シンポジストのみなさんにお言葉をいただきたいと思います。
- 例えば昨今、世界の有識者や学者の方々の近未来の予測を耳にします。例えば,「子どもたちの65%が大学を卒業後、今は存在していない職業に就く」(キャシー・デビットソン[ニューヨーク市立大学大学院センター教授])や、「今後10〜20年程度で、約47%の仕事が自動化される可能性が高い」(マイケル・A・オズボーン[オックスフォード大学准教授])、「2030年までには、週15時間程度働けば済むようになる」(ジョン・メイナード・ケインズ氏[経済学者])などのように、そんな社会になるんじゃないかと予測している方々もおられるわけです。でも、そんななかで、例えば人が主体的に学ぶということであったり、よさや美しさなどを感じ取る豊かな感性であったり、ゼロからものやことをつくりだす創造性であったりは、いろいろなことが機械に置き換わろうとも人の代わりになるものではないのだろう、そしてこれらの資質・能力は,これからますます重視されていくのだろう、という風に思います。
- 本日ご参加されているみなさんもご存じのとおり、昨年の11月20日に文部科学大臣から次の指導要領の改訂への諮問を受けて、いま中教審が様々な議論をしています。現在は議論の最中でまだ何かが決まったわけではないですが、その諮問のなかでは、グローバル化の進展や社会の職業の在り方そのものも大きく変化する可能性があるということ、これはさきほどの有識者の予測と一致するところもあるわけです。また、そうした厳しい時代をこれからの子どもたちが生きるなかで、他者と協働しながら価値の創造に挑んだり、未来を切り開く、そんな力が必要なのではないかということが言われています。そして学校教育においては、ひとつは、学ぶことと社会とのつながりにおいて、子どもたちのなかで学びと生き方が乖離することがあるのではないか。それをつなげていくこと──何を教えてどのように学ぶか、そしてどのような力が身についていくのか──、こういったことが議論されているわけです。
- そんななかで、みなさんも耳にしたことがあるかと思いますが、課題の発見・解決に向けた主体的・協働的な学び(いわゆるアクティブ・ラーニング)の充実が必要であるだろうということが、いま議論されています。学力の重要な3つの要素と関連し「何を知っているか、何ができるか(個別の知識、技能として)」、「知っていること・できることをどう使うか(思考力・判断力・表現力として)」、そして主体的に学ぶ意欲を「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか」、これら3つを「どのように学ぶか(アクティブ・ラーニング)」で実感的な学びとしてつないでいく、こういったことがこれからの社会を生きる子どもに対する教育において考えていく必要があるのではないかということで、たくさんの議論が行われています。
- そして今日の逢坂館長のお話の最後にも、起業家に必要な想像力というお話がありました。そういった幅広さも含めて、「これから鑑賞教育」はどんな方向に進んでいけばよいのか、そしてもうひとつは、この研修はこれからどういったことを目指していくのか、そんなことを最後に伺って、この会を閉じたいと思います。
- 奥村:
- 美術と教育のはざまには、広大さや豊かさと同時に偏狭さ、偏屈さ、あるいは危うさというものがあります。鑑賞教育に関する平成20年の改訂の指導方針の考え方は、「目の前にある多様で豊富な情報を理解して必要なものを選び出して、それを論理的に組み立てて協働的主体的に探究して価値を創造する」ということです。今まさに行われている教育課程改善の議論の方向とほぼいっしょなんで、先取りしているとも言えます。そういった側面は豊かさのひとつでしょう。一方、偏狭さで言うと、例えば学校教育でいろいろな鑑賞教育の現場をみていると、かたちや色をもとにイメージや主題を解釈するばかりで、豊かな知識や文脈や社会とのつながりなどは無視され、美術はもっと広いはずなのに、非常に狭いところに鑑賞教育を押し込めているという問題があります。これからの方向の一事例としては、私たちが科学研究費助成事業でやっているような、あるテーマを元に複数の作品やアクティヴィティを組み合わせた「探究的な鑑賞」などは、ひとつのブレイクスルーになるかもしれません。
- 学校には教育的な資産がかなりある。美術館にも文化的な資源が膨大にある。これらをどうつなぎあわせ組み立て直していくいかというところが大事なポイントだろうと思います。私は以前から「なぜ美術館は、美術家だけ、美術の先生だけが集まる場所なんですか」と言っています。例えば企業のエグゼクティヴとか科学の研究者とか、いろんな人たちが美術館に集まってそこでいろんなことをやるべきだ、という思いがします。同じだけ教育にもすばらしい財産──考え方や見方──があると思います。それが結実した時にどういうことが起こるのでしょう。例えば金沢21世紀美術館は多くの小学生を美術館に招待していますが、その子らがもう20歳をすぎて、いろいろなところで彼らが活躍を始めているそうです。そして、ものの見方や考え方が非常に創造的で、それが「21世紀美術館世代だね」と言われるらしいです。ということは、おそらく10年前とちがって今後そういったことがさまざまな地域で、日本全国で起こってきているのではないかと思います。
- 東良:
- ありがとうございます。三澤先生お願いします。
- 三澤:
- 教育関係者の間では、21世紀型学力ということがかなり語られています。さきほど逢坂さんの話のなかでも触れられていて、重なる部分も多いのですが、私は批判的思考というものがとても重要だと思っています。新しい文化や新しい社会をつくっていくうえで、今あることをそのまま鵜呑みにして、それを頼りにしていたら、そこからは新しいものは生まれないわけです。なんらかの批判的精神があって、それを具体的な言葉やかたちや行動に表していって、それが新しい時代や文化をつくっていくのではないかと考えた時に、その批判的思考がいちばん養われるのは美術ではないかと思います。
- なぜかというと、美術は個人的な活動で、一人ひとりの経験とか思考が、鑑賞や表現の基盤になっているからです。他の学習は基礎を習得して、その習得したものを活用して、活用の時に批判的思考力が生まれると思うのですが、美術はもともと活用から入るのではないか。自分の考え方、それまで生きてきた経験とか知識、それを元にものを見たりものを作ったりする。ということは、ダイレクトに批判的な精神がなければ作品は作れないだろう。それは、そのまま批判的思考の力になるだろうと。と同時に、批判的な思考を生み出すには、自分のなかに基軸がなければいけないわけです。この基軸というのは自分の考え方ですよね。自分の考え方をしっかりもつ。ただ自分の考え方をしっかりもつだけではだめで、他者の考え方を受け入れなければならない。
- 「開かれた個」という言葉が答申のなかにあるのですが、「開かれた個」すなわち自分自身がしっかり自立しながら他者を受け入れること、これはとくに鑑賞教育の非常に有効な学びとして、能力の獲得に貢献しているのではないか、そのように考えています。ですから、これからの在り方についても、いかに個というものをつくりだしていくか、同時に個が共有されるようなもの──個が共有されるとそれが社会になっていきますから──、個と社会の在り方を、美術を通して考えていくようなプログラムがとくに重要ではないかと考えております。
- そういう点では、美術館の事例発表がいくつかありましたけれども、例えば美術館が企画をとおして地域に関わっていくとか、均質な集団を多様な集団につなぐ──学校というのはどうしても均質な集団のなかで学びを行っており、それに対して美術館というのは社会教育のなかにありますので──、そういう施設としての機能ももっているという考え方もできます。要するに異なるものを出会わせる、同時に異なるものをつなぎあわせる、これが美術の役目であり、そういう点ではこれからますます可能性があるだろうと思っております。
- 東良:
- ありがとうございます。逢坂館長、いま美術館とのお話も出ました。それからフロアには学芸員の方もたくさんおられますが、これから美術館と学校現場をつないで鑑賞教育をいっそう深化させていく、そんな視点も含めて、これからについてお話いただけますか。
- 逢坂:
- 学校教育において、先生方が鑑賞教育を非常に熱心に実践されていることと10年以上の蓄積の成果というものに、ある種の感慨をもって伺っておりました。
- 学校教育というのは、どうしても点数をつけなくてはいけない、評価しなくてはいけない。どんな時代にもそれを変えていくのはむずかしいと思うんですけれども、その一方で、学校教育ができない部分を、私たちがある程度協調していくことができるかなと思います。今のコンピュータの社会では、すべての情報がクリックするだけで瞬時に得られる本当に便利な時代になったので、どうしても私たちの考え方が短絡的になってきています。スピーディに物事を考えなくてはいけないし、あらゆる情報を駆使して選別していかなくてはならない。たくさんの情報のなかでひとつを選んでいくということは、自分の選択眼や判断力を問われるので、なかなかむずかしいことです。ほんとうはレールの敷かれたところで、これをやりなさいと言われるほうが楽なんです。でも、今はそういう時代ではなくて、ある意味自由であり可能性はあるけれども、一方で厳しくきつい時代になってきたなと思います。そんななかで、そんなにがんばらなくても自分の考えで進んでいいんだよ、ということを、いろいろなかたちで子どもたちに伝えていく必要性があるのかなと思っています。
- 白と黒の世界にあって、じつは物事は白と黒では判断できず、グレーの部分が多い。数字ではあらわせない価値がある。そして、もしかしたらそれが非常に大切なものなのかもしれない。そういったことをいろいろな角度から伝えていくのが美術館に課せられている役目で、それがかつてに比べると増大しているのかなと思います。そのなかでさきほども少し触れたことですが、それではだれがそれを担うのか。学校の先生方もいろいろな課題があって、みなさん本当にお忙しいと思いますけれども、この国立美術館でさえ、エデュケーターの人数が非常に限られています。私たちが生きるうえでこれだけ重要な美術の世界、教育の世界にあって、それを支えていく人たちをどうやって私たちが確保できるか、育てていけるかというところで、制度的なバックアップをつくっていかなくてはいけないと思います。学校の先生も同じ問題を抱えているでしょうし、理想を語ればいろいろありますが、まずは制度的にしっかりとした整備が必要です。それから人を育てるということは、子どもたちや鑑賞者を育てることだけではなくて、それを支える人たちを育てていかなくては、これは画に描いた餅で終わってしまうのではないかなと思います。
- 東良:
- ありがとうございました。それでは、ある意味、この指導者研修の生みの親のおひとりとも言える長田先生、指導者研修は、これから全国の先生方を指導者としてもさらに育てていく、そういった役割を担っている部分も大きくあると思いますが、先生のお立場と視点から、鑑賞教育のこれからについてお話をいただければと思います。
- 長田:
- 生みの親なんてとんでもないです。また、いただいたお題に全面的に適合する答えとなるかちょっと心許ないけれども、考えていることをお話しさせていただきます。美術館と学校というふたつの機関が提携しながら、ということは、それぞれにそこで働くたくさんの人たちが提携しながら、子どもたちあるいは子どもたちの向こうのたくさんの大人たちをも巻き込んだ鑑賞教育というプログラムが発展してきた。この過程のなかで、美術館も非常に大きく変わり、学校も大きく変わってきたと思うんですね。美術館がなんであるか、ということを自ら自覚するような動きというのは全世界的にみると、すでに80年代にははっきりとみえていて、この研修でも何回かの講演でそれを紹介させてもらったことを思い出します。
- 今ちょうど国立美術館連携で「No Museum, No Life?―これからの美術館事典」という展覧会も開催されています。美術館を構成するファクターがどのようなもので成り立っているか、それぞれのファクターが美術なるものをどのようにして成立せしめているのかということを、とても興味深くスリリングに、かつわかりやすく展示をしていただいているのは、日本の美術館が、美術館とはなんであるかということをリフレクションしながら、新たな展開をはじめていることの象徴のようなものだと思うんですね。美術館はあるひとつの価値を展示によって、あるいは研究をとおして世に問うという活動を行っていますが、そこでの「見る」という営みもまた、美術館がこういうふうに示してくれるから、「ああ、そうですか」と受け取る行為では本来なかった。キャプションや解説パネルを読んで、そのとおりに作品をなぞっていくということではなかったということを、この10年間、学校もかかわりながら、いろいろと蓄積してきたわけです。つまり、一人ひとりの子どもが、自分が感じたこと、自分がみつけたこと、これを自分の言葉にしていく。周りの仲間たちと語り合い、「ああ、もっとこういう見方もあるんだ」ということにどんどん気がついていって、そして常に自分に立ち戻りながら、自分が納得のいくものの見方をよりどころとしながら、「この作家はその当時、こんなことで苦労していたんだ」とか、「この作品の造形的な新しさはここにあるんだ」ということなどを知ることによって、自分の獲得した見方を一挙に深め、かつ、自らクリティックに見る、という経験です。この10年間、全国各地の美術館、学校と連携した一連の鑑賞プロジェクトのなかで、このような経験が深まってきたのだと思うのです。これは要するに、美術館という美術を提示する機関を通して、美術は、ほんとうはどこで成り立つのかということを、子どもたち一人ひとりが自分でつかみとっていく経験をしはじめたということだと思います。
- もう一歩踏み込んで言えば、美術であるのか美術でないのかということを、子どもたち自身が一人ひとり判断していく素地を培いつつあるということでした。これをさらにもう1回言うと、子どもたちがそれぞれの「感性に基づいて」、という時の感性が、ほんとうに自分の感性になる、ということを始めることなのだと思います。つまり、自分の感性は最初からあてがわれてあるわけでもないし、生まれながらの感性そのままであるわけでもない。様々な感性的な経験と教育をくぐり抜けながら、批判的につかみとって、より深くより高く、そしてクリエイティヴでクリティカルなものになっていく、そのようなことが始まるということなんだ、と。こういうことが行われて確実に広がっていくとすれば、21世紀型の能力として求められる最大のクリエイティヴィティというのがここに確保できる。それはたんに見方というレベルだけではなく、プロジェクトしていく、つまり今までに何もない新しい可能性を想像していく、イメージし、かつクリエイトしていく、「デザイン・シンキング」といわれるようなことにも通じる活動のベースにもなっていく。そのぐらいに大きなことを、ごく一部のエリートの子どものためにでなくて、全日本的な広がりの子どもの元で培っていく可能性を開きつつある。次の10年、そういうかたちで実っていくことを切に願っているといったところです。
- 東良:
- ありがとうございました。今日の多岐にわたる示唆に富んだご発言をひとつにまとめるのはむずかしいのですが、ひとつだけ言えるのは、今後いっそう「子ども」を主語として鑑賞教育をどう考えていくのか、ここには変わりないと思うんですね。学校現場と美術館との間の温度差について発表のなかでも指摘がありましたが、それでもやはり、子どもの学びを真ん中に据えて子どもたちを育てるという視点はどの立場でも変わりはない。また、そのような鑑賞教育が今後求められていくのだろうと思いますし、子どもたちの見方や感じ方が多様であったり、長田先生のお話にもありましたが、子ども一人ひとり感性の違いがあるなかで、当然鑑賞や教育の在り方だって、ひとつの型があるわけではなく、様々な方法があるのだろうと思います。そういったことを今後よりいっそう追究しながら、全国の子どもたちが鑑賞を通して様々なことを学び、自分の中に様々な意味や価値を生み出していく、そういった鑑賞を通した教育を今後一層推進していく。そのためには、この指導者研修でそういった指導者を育てていく役割がまだまだ大きくあるんじゃないか。司会進行させていただきながらそんなふうに思いました。 今日はどうもありがとうございました。
プロフィール
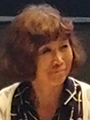 逢坂恵理子(おおさか えりこ)
逢坂恵理子(おおさか えりこ)
横浜美術館館長。東京生まれ。国際交流基金、ICA名古屋、水戸芸術館現代美術センター、森美術館を経て、2009年より現職。第49回ヴェニス・ビエンナーレ日本館コミッショナー、ヨコハマトリエンナーレ2011総合ディレクター、横浜トリエンナーレ組織委員会委員長を務めるなど、多くの現代美術国際展をてがける。
 奥村高明(おくむら たかあき)
奥村高明(おくむら たかあき)
聖徳大学児童学部長・教授 博士(芸術学)。1958年宮崎生まれ。公立小中学校教員、宮崎県立美術館学芸員、文部科学省教科調査官を経て、2011年より現職、14年より学部長。日本教材備品協会理事、美術科教育学会理事、NTTドコモなどの児童生徒作品展の全国審査員長等を務める。
 長田謙一(ながた けんいち)
長田謙一(ながた けんいち)
名古屋芸術大学大学院教授。岩手大学、千葉大学、首都大学東京を経て、2013年より現職。主な編著に『近代日本デザイン史』(美学出版、2006)、主な訳書に『美術館活用術 鑑賞教育の手引き ロンドン・テートギャラリー編』(美術出版社、2012)等。
 三澤一実(みさわ かずみ)
三澤一実(みさわ かずみ)
武蔵野美術大学教授。1963年長野生まれ。公立小中学校教員、埼玉県立近代美術館学芸員、文教大学を経て、2008年より現職。「図画工作・美術なんでも展覧会」(うらわ美術館、2007)、「旅するムサビ」プロジェクト等、美術館と学校との連携及び地域との連携活動の研究に従事。
 東良雅人(ひがしら まさひと)
東良雅人(ひがしら まさひと)
文部科学省教科調査官。1962年京都生まれ。1987年京都市立の公立中学校の美術科教諭として赴任。 その後、京都市の公立小学校図画工作の専科を担当。 2002年から11年3月まで京都市の教育委員会で指導主事を務める。 2011年4月より現職。
